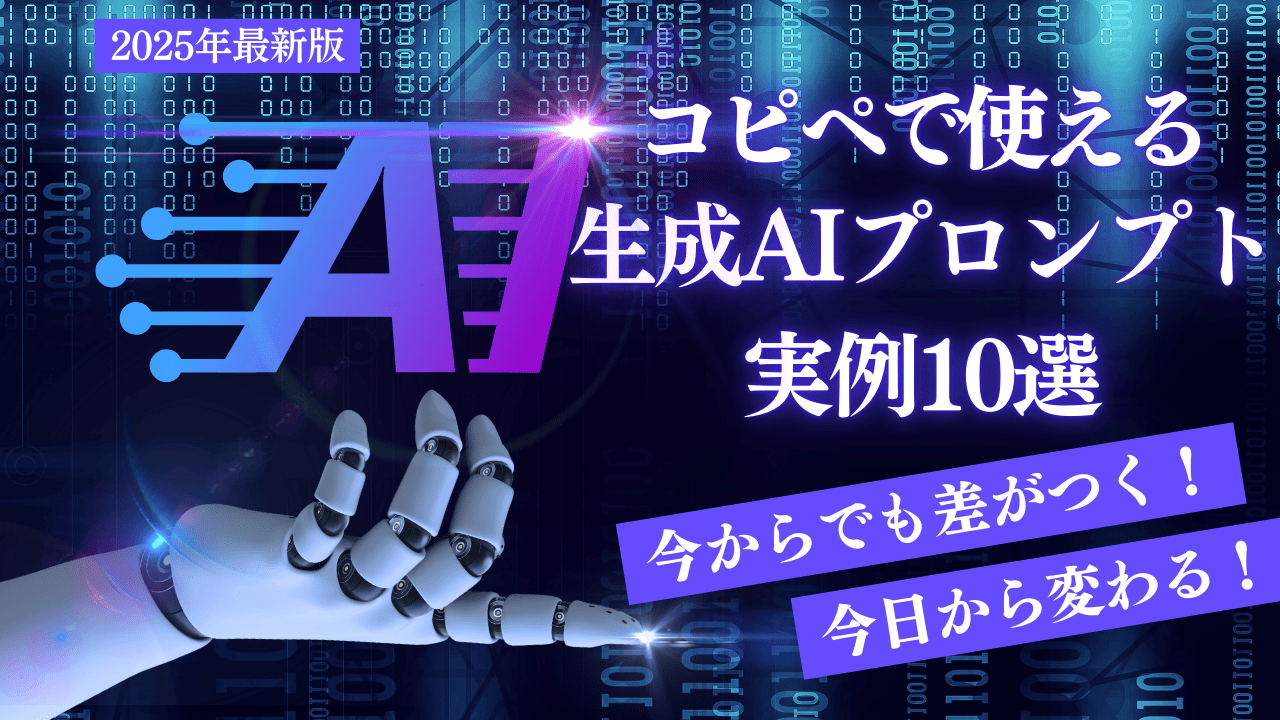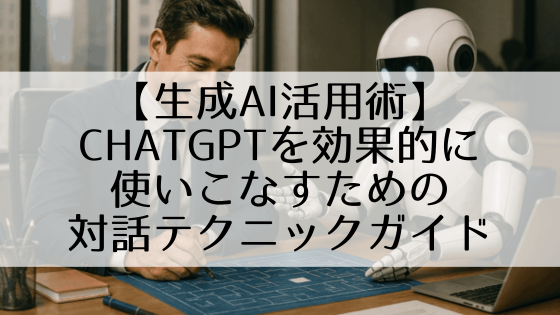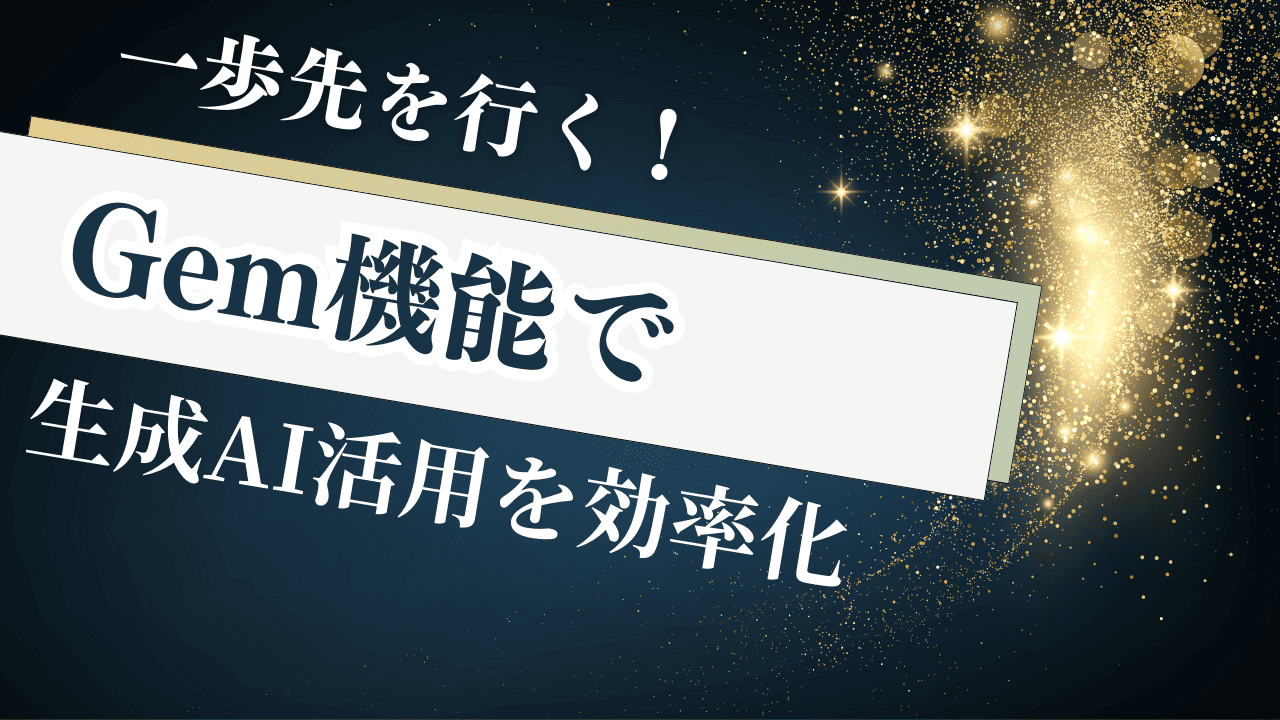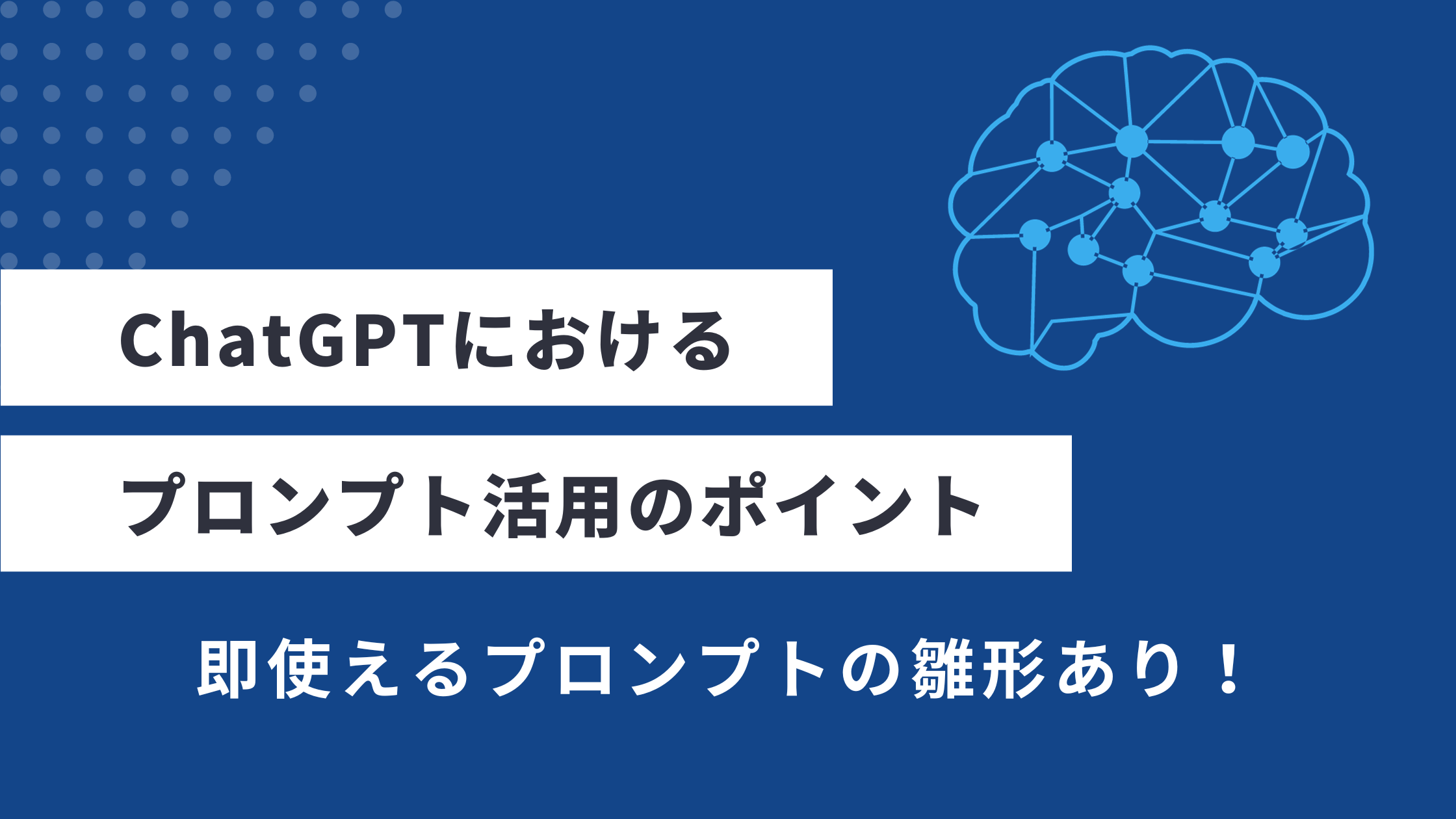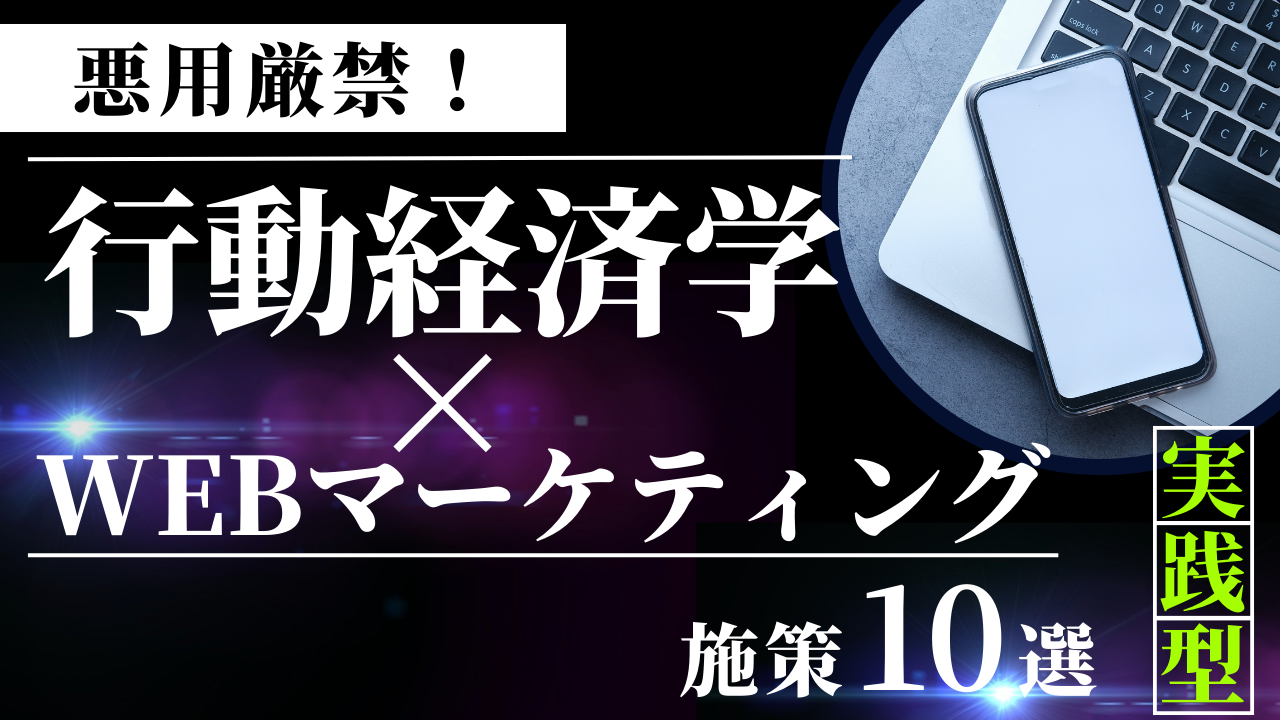コンサルティング部 トップコンサルタント
面倒な仕事から解放される頼れる相棒、それが生成AI
こんにちは!グローカルマーケティングの武田です!皆さん、毎日の業務に追われていませんか?会議の準備、資料作り、メール対応・・・やることは山積みなのに時間は足りない。そんな悩みを抱えている方に朗報です!2022年11月に登場したChatGPTをはじめとする生成AIは、あなたの「頼れる相棒」になってくれるかもしれません。
「でも自分には関係ない」なんて思っていませんか?実は中小企業や現場従業員、建設・卸・小売・サービス業など、あらゆる業種で生成AIを上手く導入することで、生産性が劇的に改善し、人手不足の解消にも繋がるんです。
この記事では、2025年4月時点で本当に役立つ、明日から使えるような生成AI活用法を具体的にご紹介します!なお弊社では、「生成AI活用」について30分無料オンライン相談を承っています。ちょっとした事の確認・相談でも大丈夫ですので、組織全体での効果的な導入方法や具体的な運用についてお気軽にご相談ください。
2025年6月~9月無料オンラインセミナー情報: 実践的DXセミナー
▼ 目次はコチラ ※クリックすると該当の箇所までスクロールします。
Table of Contents Plus
- 1 生成AIは魔法ではなく、使えば使うほど上達する道具
- 2 明日から使える!生成AI活用テクニック10選
- 2.1 1. 「敬語が不安…」そんなメール作成の悩みを解消!
- 2.2 2. 「この稟議書、通るかな…」承認率アップの文書作成法
- 2.3 3. 「また議事録係か…」会議後の作業を激減させる裏ワザ
- 2.4 4. 「企画書、何から書けばいいの…」アイデアが湧き出る構成術
- 2.5 5. 「社内マニュアルが古くて使えない…」簡単アップデート術
- 2.6 6. 「競合分析、データ多すぎ…」情報整理を効率化する方法
- 2.7 7. 「外国人顧客、言葉が通じなくて…」多言語対応を一人で乗り切る
- 2.8 8. 「この数字、何か傾向あるの?」データから洞察を引き出す魔法
- 2.9 9. 「SNS投稿のネタ切れ…」簡単に心を掴むコンテンツ作成術
- 2.10 10. 「事業計画、何から書けばいいの…」小規模経営者のための戦略立案術
- 3 ~なぜ日本企業は生成AIの活用が遅れているの?
- 4 生成AIの最初の一歩:小さく始めて大きく育てる
- 5 生成AIとうまく付き合うための3つの注意点
- 6 まとめ:明日から実践!あなたの生成AI活用、ここから始まる
生成AIは魔法ではなく、使えば使うほど上達する道具
生成AIを仕事に活かすコツは、「魔法の箱」と思わないことです。生成AIは使い手の腕前で決まります。正直に言うと、最初はうまくいかないことも多いでしょう。でも大丈夫。毎日ちょっとずつ使っていくうちに、徐々に「生成AIの使い方」が上達していきます。
私自身、最初に生成AIで文章を作った時と、今とでは雲泥の差があります。生成AIが微妙な回答をしてきたら「生成AIのせい」ではなく「自分の指示の仕方が悪かったんだな」と考えて、プロンプト(指示)を改良していくんです。
「サボりたい」という気持ちは、実はとっても大切です!面倒な仕事を効率的に終わらせたい気持ちが、生成AI時代の原動力になります。生成AIを「デキる部下」として扱い、適切な指示を出す練習をしていきましょう。
それでは、明日から使えるような具体的な生成AI活用テクニックを見ていきましょう!
明日から使える!生成AI活用テクニック10選
そのままコピペで使えるプロンプト(生成AIへの指示)入力例を用意しました。コピペしてお試しください。自分のやりたいことを伝えるアレンジ力が肝ですよ!
1. 「敬語が不安…」そんなメール作成の悩みを解消!
よくある悩み: メールの敬語が合ってるか不安・・・「〜させていただきます」の使いすぎじゃないか心配・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の要素をもとに、【社外の新規取引先】向けの丁寧なビジネスメールを作成してください。
重要なのは、過剰な「させていただく」を避け、簡潔で読みやすいことです。
# 状況設定
- 私:株式会社〇〇ソリューションズの営業部 佐藤
- 相手:△△商事の購買部長 鈴木様(初めてのやり取り)
- 目的:先日お送りした見積書について、ご検討状況を確認したい
# 含めるべき要素
- 見積書送付から1週間経過
- 来週金曜日までに返答いただけると助かる
- 不明点があれば説明の機会をいただきたい
# トーン・文体
- 丁寧だが堅すぎない
- 一文は30字程度で簡潔に
- 「〜させていただく」は最大1回までこれが「プロンプト」です!単に「メールを書いて」と頼むのではなく、①状況設定 ②含めるべき要素 ③文体指定 と3つのポイントに分けて指示すると、格段に質の高い文面が得られます。特に「させていただく」のような敬語の過剰使用を制限する指示を入れると、読みやすいメールになります。
実際の声: 「上司から『メールが長すぎる』『敬語が不自然』とよく指摘されていました。でも生成AIに適切な指示を出す方法を覚えてからは、『最近のメール、簡潔でいいね』と褒められるように!時間も1/3に減って一石二鳥です」(27歳・IT企業営業)
2. 「この稟議書、通るかな…」承認率アップの文書作成法
よくある悩み: 稟議書や申請書が何度も差し戻される・・・上司や経営層を納得させる論理構成ができない・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の内容で稟議書の下書きを作成してください。特に「なぜ今これが必要か」を説得力を持って伝えることを重視してください。
# 基本情報
- 申請事項:営業部へのノートPC5台追加購入
- 予算:総額85万円(1台17万円×5台)
- 申請者:営業部長 山田
# 主張すべきポイント
- モバイルワーク環境の不足で、客先でのプレゼンや提案書作成に支障
- 現在、営業8名で3台のノートPCを共有しており、スケジュール調整が困難
- 昨年度に比べ客先訪問が30%増加
# 想定される反論と対策
- 「タブレットでよいのでは?」→CAD図面の編集や大量データ処理が必要
- 「予算が高すぎる」→堅牢性と3年保証込みの業務用モデルを選定
- 「今すぐ必要?」→次月の大型プロジェクト5件の提案作業に必要
# 文体・構成
- 箇条書きより文章で、論理的に
- 数値データを効果的に活用
- 将来的な業績向上効果も言及稟議書で大切なのは「論理構造」と「想定反論への対策」です。このプロンプトでは、特に稟議書が差し戻される原因となる「想定される反論と対策」をあらかじめ指示しておくことで、説得力のある文書が完成します。さらに「文体・構成」で具体的に指示することで、組織内で評価される文書スタイルに近づけることができます。
実際の声: 「IT機器の導入稟議が3回連続で却下されていましたが、生成AIを使って『想定反論への対策』を盛り込んだ稟議書を作成したところ、一発承認されました。経営層の視点で書けるようになったのが大きいです」(38歳・製造業・情報システム部)
3. 「また議事録係か…」会議後の作業を激減させる裏ワザ
よくある悩み: 会議の議事録作成が面倒・・・要点がまとまらない・・・アクションアイテムが不明確・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の会議メモから、以下の4つのセクションに分けた構造化された議事録を作成してください:
1) 会議概要(日時・参加者・目的を含む)
2) 議題ごとの討議内容(各議題の結論を太字で強調)
3) 決定事項(箇条書きで簡潔に)
4) アクションアイテム(担当者・期限つきで一覧化)
# フォーマット指定
- アクションアイテムは「誰が・何を・いつまでに」の形式で統一
- すべての発言をそのまま書き起こすのではなく、重要ポイントを抽出
- 「えーと」「あのー」などの言い淀みは削除
- 全体で800字以内にまとめる
# 会議メモ:
[ここに録音の書き起こしや会議メモを貼り付け]このプロンプトのコツは、単に「議事録を作って」と頼むのではなく、「構造」と「フォーマット」を明確に指定すること。特に「アクションアイテムは『誰が・何を・いつまでに』の形式で統一」という指示がポイントで、これにより会議後の行動計画が明確になります。また「全体で800字以内」と指定することで、冗長になりがちな議事録を簡潔にまとめられます。
実際の声: 「毎回90分以上かかっていた議事録作成が、生成AIを使うようになってから15分で終わるようになりました。しかも『アクションアイテムがわかりやすい』と上司から評価されて、会議の生産性そのものも上がりました」(32歳・サービス業・管理部門)
4. 「企画書、何から書けばいいの…」アイデアが湧き出る構成術
よくある悩み: 企画書や提案書のネタが思いつかない・・・構成がまとまらない・・・説得力がない・・・
プロンプト入力例:
# 指示
新規事業企画書の構成案を作成してください。特に「競合との差別化」と「収益モデル」の説得力を重視します。
# プロジェクト概要
- 企画名:地方特産品のサブスクリプションサービス「旬鮮ボックス」
- ターゲット:30〜40代の共働き世帯、食にこだわりがある都市部在住者
- 予算:初期投資300万円、月間運営コスト50万円
# 競合状況
- A社:全国の名産品を扱うが、配送頻度が月1回固定
- B社:有機野菜専門のサブスク、価格帯が高め(月6,000円〜)
- C社:大手ECの定期便サービス、商品パーソナライズ機能なし
# 差別化ポイント
- AIによる好み学習と推薦機能
- 週1回の少量多品種配送(食品ロス削減)
- 生産者とのオンライン交流会
# 実現のカギ
- 地方自治体3県との連携協定
- 物流会社との専用便契約
- 月額3,980円の価格設定
# 構成の条件
- SWOT分析を含める
- 市場規模・成長性のデータを効果的に活用
- 5年間の収支計画を含める
- 実証実験の計画も具体的に企画書作成でつまずくのは「構成」と「差別化ポイント」です。このプロンプトでは、「競合状況」と「差別化ポイント」を明確に指示することで、生成AIがより実践的な企画書構成を提案します。さらに「構成の条件」で分析フレームワークやデータの活用方法を指定すると、説得力のある企画書の骨組みができあがります。
実際の声: 「新規事業のアイデアはあったけど、どう企画書にまとめていいか分からず、先送りにしていました。生成AIに競合状況まで整理して指示したら、『これなら通るかも』と思える構成案が10分で出来上がり、実際に経営会議で承認されました!」(41歳・小売業・企画部)
5. 「社内マニュアルが古くて使えない…」簡単アップデート術
よくある悩み: マニュアルの更新が追いつかない・・・新人が理解できるレベルに噛み砕けない・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の既存マニュアルを、以下の3点を重視してリライトしてください:
1) 2025年の最新情報に更新
2) 新入社員でもわかる平易な説明に変換
3) チェックリスト形式で実行しやすく再構成
# 対象読者
- 入社1ヶ月目の営業事務(20代)
- PCスキルは基本操作のみ
- 業界知識はまだ乏しい
# 課題点
- 専門用語が多くて理解しづらい
- 手順が文章のみで視覚的でない
- システム画面が古い(2018年版)
# 改善方針
- 専門用語には必ず簡単な説明を括弧書きで追加
- 重要な手順は番号付きリストに変換
- 「よくある間違い」セクションを追加
- 各セクションの冒頭に「これができるようになります」目標を明記
# 既存マニュアル:
[ここに古いマニュアルテキストを貼り付け]マニュアル更新の決め手は「対象読者」と「課題点」を明確にすること。このプロンプトでは特に「対象読者」の知識レベルや背景を詳細に指定することで、適切な難易度のマニュアルが生成されます。また「改善方針」で具体的な表現方法(括弧書きでの説明追加など)を指示すると、より実用的な内容になります。
実際の声: 「毎年の業務マニュアル更新が大きな負担でしたが、生成AIを使って古いマニュアルをインプットし、最新情報に更新してもらったところ、これまで1週間かかっていた作業がたった1日で完了。新人からも『とても分かりやすい』と好評です」(45歳・金融業・研修担当)
6. 「競合分析、データ多すぎ…」情報整理を効率化する方法
よくある悩み: 大量の情報から重要ポイントを見つけられない・・・分析の視点が偏る・・・プレゼンで説得力がない・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の当社と競合3社の情報をもとに、次の3つの視点で分析してください:
1) 各社の強み・弱み比較(SWOT形式)
2) 戦略的な差別化ポイント抽出(3つに絞る)
3) 当社が取るべき戦略の提案(守りと攻めの両面)
# 分析フレームワーク
- 単純な表形式ではなく、相互関連性がわかる分析に
- 「顧客視点」を重視した評価
- 数値データがある項目は、グラフ化を想定した比較方法を提案
- 業界トレンドも踏まえた将来予測も含める
# 当社情報
[会社概要、製品情報、市場シェア、顧客評価データなど]
# 競合A社情報
[同様の情報]
# 競合B社情報
[同様の情報]
# 競合C社情報
[同様の情報]
# 重視すべき評価軸
- 価格競争力よりも顧客体験の質を重視
- 短期的利益よりも顧客維持率を重視
- テクノロジー活用度の比較競合分析のコツは「分析フレームワーク」と「評価軸」の明確化です。このプロンプトでは「単純な表形式ではなく相互関連性」「顧客視点を重視」など、より洗練された分析手法を指定。さらに最後の「重視すべき評価軸」で会社の価値観や戦略方針を伝えることで、より自社の実情に合った分析結果が得られます。
実際の声: 「四半期ごとの競合分析レポートの作成に毎回3日かかっていましたが、生成AIを活用したことで1日で完了するようになりました。しかも『顧客視点』という新たな切り口を取り入れたことで、営業戦略の見直しにつながる洞察が得られました」(36歳・IT企業・マーケティング担当)
7. 「外国人顧客、言葉が通じなくて…」多言語対応を一人で乗り切る
よくある悩み: 急な外国人対応に焦る・・・ニュアンスが伝わらない・・・翻訳会社に頼むと時間もコストもかかる・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の日本語テキストを英語と中国語(簡体字)に翻訳してください。
特に以下の点に注意してください:
- 業界専門用語の正確な翻訳
- 日本特有の表現は現地の方に伝わる表現に置き換える
- ビジネス文書として適切な丁寧さを維持
- カジュアルすぎる表現や直訳による不自然さを避ける
# 翻訳対象テキスト
[ここに翻訳したい日本語テキストを貼り付け]
# 専門用語リスト(翻訳維持のため)
- 「□□工法」→「□□ Method」
- 「××システム」→「×× System」
- 「△△認証」→「△△ Certification」
# カルチャライズすべき表現
- 「お手数をおかけしますが」→ビジネス英語・中国語での自然な表現に変換
- 「よろしくお願いいたします」→目的に応じた締めの表現に
- 「弊社」→一人称単数/複数の適切な表現に翻訳の質を高めるコツは「専門用語リスト」と「カルチャライズすべき表現」の指定です。特に日本語特有の「お手数をおかけしますが」「よろしくお願いいたします」などの表現は直訳すると不自然になるため、目的に応じた表現への変換を指示します。専門用語は正確に維持するよう明示的に指定することで、業界特有の用語も適切に翻訳されます。
実際の声: 「海外からの問い合わせメールへの返信を、これまで外部の翻訳会社に依頼していましたが、生成AIを使うことで翻訳コストが月10万円削減できました。しかも以前は2日かかっていた返信が、当日中にできるようになり顧客満足度も向上しています」(39歳・製造業・海外営業)
8. 「この数字、何か傾向あるの?」データから洞察を引き出す魔法
よくある悩み: エクセルには詳しくない・・・このデータから何が言えるかわからない・・・上司に説得力ある報告ができない・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の売上データを分析し、次の3つの視点でインサイトを抽出してください:
1) 最も重要な3つのトレンドや傾向(データに基づいて)
2) 予想外の発見や異常値とその考えられる理由
3) 具体的な売上改善のための3つのアクションプラン
# 分析の焦点
- 単なる数値の羅列ではなく、「なぜそうなっているのか」の考察を含める
- グラフ化すべきデータの組み合わせも提案
- 平均値だけでなく、分布や外れ値にも注目
- 前年同期比や季節変動の影響も考慮
# データの文脈情報
- 小売業の月次売上データ(直近12ヶ月分)
- 4月に新商品ライン投入
- 6月から新たな販売促進キャンペーン開始
- 8月に主要競合の撤退あり
# 売上データ:
[ここに売上データをコピペ]データ分析で差がつくのは「分析の焦点」と「データの文脈情報」の指定です。単に「分析して」と言うのではなく、「なぜそうなっているのか」の考察や、「グラフ化すべきデータの組み合わせ」といった具体的な指示を出すことで、より実用的な分析結果が得られます。また「データの文脈情報」で商品投入やキャンペーンなどの背景情報を与えることで、数字の背後にある要因を考慮した深い分析が可能になります。
実際の声: 「毎月の売上レポート作成が苦手で、いつも『前月比○○%増加』といった表面的な報告しかできていませんでした。生成AIを使った分析手法を覚えてからは、『なぜ増加したのか』『どの商品カテゴリが貢献したのか』といった踏み込んだ分析ができるようになり、営業会議での発言にも説得力が増しました」(34歳・小売業・店舗マネージャー)
9. 「SNS投稿のネタ切れ…」簡単に心を掴むコンテンツ作成術
よくある悩み: 毎日の投稿が負担・・・フォロワーが増えない…いいねやコメントが少ない・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の条件で、Instagram投稿用のキャプション5案を作成してください。
それぞれ異なるアングルからアプローチし、バリエーションを持たせてください。
# 投稿テーマ
- カフェの新メニュー「抹茶ティラミスパフェ」の紹介
# ターゲット層
- 20〜30代女性
- スイーツ好き
- 写真映えを重視する層
# 投稿の目的(優先度順)
1. 来店喚起(特に平日午後の集客)
2. 投稿のシェア促進
3. 当店の高品質素材へのこだわりアピール
# 表現スタイル
- 一人称(「私たち」「当店」)で親しみやすく
- 1案あたり70〜100文字
- 質問やコールトゥアクションを必ず含める
- 絵文字は3〜5個程度自然に取り入れる
- 最初の一文で興味を引く工夫を
# ハッシュタグ
- 投稿ごとに5〜7個の関連ハッシュタグ提案
- 一般的なもの(#カフェ巡り)と特徴的なもの(#抹茶ティラミス)をバランスよくSNS投稿で差がつくのは「投稿の目的」と「表現スタイル」の明確化です。このプロンプトでは目的を優先度順に指定し、「来店喚起」が主目的であることを明確にしています。また「一人称で親しみやすく」「最初の一文で興味を引く」など具体的な文体指示により、ブランドの雰囲気に合った自然な投稿文が作成できます。ハッシュタグの指定まで含めることで、投稿後すぐに使える完成度の高い文章が得られます。
実際の声: 「SNS運用が本当に苦手で、いつも同じような投稿になっていました。生成AIを使うようになってからは、バリエーション豊かな投稿ができるようになり、エンゲージメント率が3倍に増加!特に『質問』を含めるテクニックでコメント数が増え、お客様との対話が増えました」(29歳・カフェオーナー)
10. 「事業計画、何から書けばいいの…」小規模経営者のための戦略立案術
よくある悩み: 事業計画書を作るのが苦手…将来の展望をうまく言語化できない…銀行や支援機関に説得力ある計画を提示できない・・・
プロンプト入力例:
# 指示
以下の情報をもとに、小規模事業者向けの3年間の事業計画書の骨子を作成してください。
特に「実現可能性」と「差別化戦略」に重点を置いた、金融機関提出用の説得力ある計画にしてください。
# 事業概要
- 業種:町の小さな洋菓子店(創業5年目)
- 従業員:オーナー含め4名(パート2名)
- 現状:月商約200万円、店舗面積25坪、昨年比売上5%増
# 現状の課題
- 週末の来客数は多いが平日が閑散
- 競合店の出店により客単価が下がっている
- SNSでの認知度は高いが、リピート率に課題
- 原材料費高騰による利益率の低下
# 強み・機会
- オーナーパティシエの技術力(コンテスト入賞歴あり)
- 地元産フルーツとの取引関係確立
- 駅前再開発による周辺人口増加予定(来年以降)
- ECサイト運営の経験あり(現在は休止中)
# 計画に含める要素
- 売上・利益の数値目標(年度別、現実的な成長率で)
- 具体的な施策(価格戦略、商品開発、販路拡大など)
- 必要な設備投資や人材採用の計画
- 資金計画(借入返済計画も含む)
- 想定されるリスクとその対応策
# 文体・形式
- 感情的な表現より具体的なデータと論理的な説明を重視
- 業界用語は最小限に、金融機関担当者にも理解しやすく
- グラフや表を活用したビジュアル提案を意識
- 1項目あたり3〜5行程度の簡潔な記述事業計画作成のコツは「現状の課題」と「強み・機会」を明確に整理すること。このプロンプトでは特に「課題」と「強み」を具体的に列挙し、生成AIが実態に即した現実的な計画を立案できるようにしています。また「文体・形式」で「感情的な表現より具体的なデータと論理的な説明を重視」と指定することで、金融機関や支援機関から評価される客観的な計画書が作成できます。日々の経営に追われて中長期計画を練る時間がない小規模経営者にとって、これは大きな助けになります。
実際の声: 「日本政策金融公庫の融資申請に向けて事業計画を作成する必要があり頭を抱えていました。生成AIに自店の情報を整理して入力したところ、驚くほど実現可能性の高い3年計画が短時間で完成。数字だけでなく『なぜその施策が有効か』という論理的な説明も含まれていたため、審査担当者からも『よく考えられた計画ですね』と評価され、希望通りの融資が実現しました」(47歳・洋菓子店オーナー)
【プロンプトのヒミツ:
~おまけ~#と-の役割】
この生成AIへの指示文(プロンプト)で見かける#や-は、実は人間が生成AIに「こうしてほしい!」をスムーズに伝えるための工夫なんです。#は話の大きなテーマ(見出し)を、-は具体的なお願いごと(箇条書き)を伝えるのに使っています。まるで整理されたメモのように、生成AIも指示を理解しやすくなるんですね。
~なぜ日本企業は生成AIの活用が遅れているの?
日本における個人の生成AI利用率はわずか9%にとどまっており、米国の40%超、中国の60%近くと比較すると、その差は歴然としています。※出典:「令和6年版情報通信白書」(総務省)第5章デジタルテクノロジーの浸透 図表Ⅰ-5-1-1 生成AIの利用経験より
「うちの会社では無理だよ…」そう思っているあなた、実はその思い込みが最大の障壁かもしれません。日本企業の生成AI活用が遅れている主な理由は以下の3つです。
1. 「具体的に何ができるの?」活用イメージの欠如
業務での活用を検討している企業の37.8%が「現時点では活用イメージが湧かない」と回答しています。
「生成AIっていっても何から始めればいいの?」「うちの業種でどう使えるんだろう?」そんな声をよく聞きます。確かに「ChatGPTで業務効率化!」と言われても、具体的なイメージが湧かなければ一歩を踏み出せませんよね。でも実は、この記事で紹介したように、メール作成や議事録整理など、どんな業種でも共通する日常業務からスタートするのが近道なんです。
2. 「日本の商習慣には合わないのでは?」文化的な壁
「生成AIが敬語や謙譲語を適切に使えるのか」「日本特有の稟議書や根回しの文化を生成AIが理解できるのか」という懸念も根強くあります。しかし、適切なプロンプト(指示)を与えることで、生成AIは驚くほど日本のビジネス慣行に適応します。実際、敬語の使い分けや稟議書作成は、構造が明確なため、むしろ生成AIが得意とする分野なのです。
3. 「情報漏洩が心配…」セキュリティへの過度な懸念
「セキュリティリスクの拡大」を心配する企業が多く、機密情報保護に関する不安が導入の足かせとなっています。
確かにセキュリティは重要な懸念事項です。しかし「だから生成AI全面禁止」という極端な対応ではなく、「何を入力してよいか/いけないか」のガイドラインを設けることで、多くの業務で生成AIを安全に活用できます。また個人情報を匿名化するなど、工夫次第で安全に生成AIの恩恵を受けられるのです。
生成AIの最初の一歩:小さく始めて大きく育てる
「百聞は一見に如かず」。何より大切なのは実際に使ってみること。まずは次のような特徴を持つ業務から始めてみましょう。
- 日常的に行う作業 – 毎日のメール作成や週次レポートなど、頻度の高い業務
- 定型的なパターンがある – 形式が決まっている文書作成や情報整理
- じっくり確認できる – すぐに外部に提出するものではなく、自分で内容を確認できるもの
- 失敗しても大きな問題にならない – 内部向けの下書きや企画のたたき台など
「こんな簡単なことに生成AIを使うなんて…」と思うかもしれませんが、最初から複雑な業務に挑戦するよりも、日常の小さなタスクでコツを掴むことが近道です。一つ一つの小さな成功体験が、より高度な活用へとつながっていきます。
生成AIとうまく付き合うための3つの注意点
1. まずは匿名化・一般化してから入力を
プライバシーや機密情報を守るための簡単なコツ:入力前に個人情報や機密情報を一般化しましょう。
具体例:
❌ 「田中太郎様(○○自動車購買部長)への見積書を作成して」
⭕ 「A社(大手自動車メーカー)の購買部長への見積書を作成して」
これだけで、情報漏洩リスクを大幅に減らしながら、同等の結果が得られます。
2. 生成AIは「下書き作成係」と思って
生成AIの出力はあくまで「たたき台」です。特に数字や専門知識、法的な内容については、必ず自分の知識と経験で確認しましょう。時に生成AIは自信満々に間違った情報を述べる「ハルシネーション」を起こすことがあります。でも逆に考えれば、「完璧な回答」を期待せず、「下書き作成係」として活用することで、生成AIの真価が発揮されるのです。最終判断は常に人間が行う、このバランスが生成AI活用の鍵です。
3. 継続的な学習とノウハウの蓄積を
生成AIを活用するスキルは、継続的な練習と経験の積み重ねで向上します。社内でのプロンプト事例や成功体験を共有するための仕組みを作りましょう。例えば、社内Wikiやチャットツールに「生成AIプロンプト集」チャンネルを作り、効果的だったプロンプトを共有することで、組織全体の生成AI活用スキルが向上します。また、定期的に「生成AI活用ランチ会」などを開催し、メンバー同士で新しい活用法やコツを共有することで、生成AIとの協業文化を育てていくことができます。一人ひとりの小さな発見が、組織全体の大きな変革につながるのです。
まとめ:明日から実践!あなたの生成AI活用、ここから始まる
生成AIは上手く活用すれば、生産性が大幅に向上することが予想されます。中小企業や、現場従業員、建設・卸・小売・サービス業といった業種に上手く導入することができれば、生産性が改善し、人手不足が少しでも改善されると、日本全体の生産性が向上する可能性が高そうです。まずは、使ってみるところからでも始めて、生成AI活用を広めていくことが大切ですね
生成AIとの付き合い方で最も大切なのは「使い手の腕次第」という認識です。魔法の杖ではなく、使えば使うほど上達する道具として向き合いましょう。そして「これ、面倒だな」と感じる業務こそ、生成AIの出番です!
明日から始める3ステップ:
- 今日学んだプロンプトテクニックを試してみる – この記事のプロンプト例を参考に、まずは自分の日常業務で試してみましょう
- プロンプトのレシピ集を作る – うまくいったプロンプトはメモやファイルに保存しておくと、次回からさらに効率的です
- 小さな成功体験を同僚と共有する – 「これ、便利だよ」と伝えることで、組織全体の生成AI活用が広がります
「完璧な生成AI活用」を目指すのではなく、「少しずつ楽になる工夫」を積み重ねていくことが成功の秘訣です。生成AIはあなたの仕事を奪う脅威ではなく、面倒な作業から解放してくれる心強い味方。今日から一歩踏み出して、あなたらしい働き方を見つけてみませんか?
この記事が生成AI活用の第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。ご質問やご意見、実際に試してみた感想などがあれば、ぜひお聞かせください!
▶なお弊社では、「生成AI活用」について30分無料オンライン相談を承っています。ちょっとした事の確認・相談でも大丈夫ですので、組織全体での効果的な導入方法や具体的な運用方法についてお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!